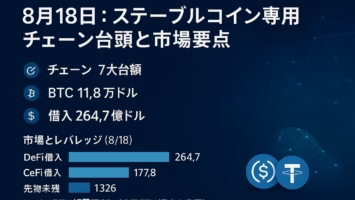▽ 要約
貸暗号資産 … 金商法監督化を提示、抜け穴封じへ。
金商法 … 再貸付・委任検証の管理と開示を義務化。
新規交換所公募(IEO) … 年50万円超は年収・純資産の5%(上限200万円)案。
発生事項 … 虚偽記載に罰則・課徴金、内部者取引規制も。
金融審議会WGは、暗号資産レンディングの抜け穴を塞ぐため金商法で監督し、分別管理・リスク説明を義務化、併せてIEO投資上限や虚偽記載の罰則案を示した。
レンディング金商法化とIEO投資上限
交換業の管理外だった借入スキームが利用者保護を損ねたため、金商法での登録・監督とIEO投資上限の導入が同時に提案された。
レンディングは第一種金融商品取引業等として登録・監督の射程に入り、再貸付・ステーキング時のリスク管理体制が義務化される見込みだ。さらに、顧客資産は分別管理や信託保全、コールドウォレット等の安全保管を求める方向で、ハッキング・倒産時リスクの低減を図る。勧誘・広告では元本割れや返還不能、途中解約不可などの重要事項説明が法定化され、過大広告の禁止も盛り込まれる。対象範囲は「対公衆性のある貸付」で、機関投資家間の相対は除外する案が示された。
要点
2025-11-07に制度案が整理されたため、年内取りまとめ→2026通常国会に法案提出→2026–27の順次施行が基本線となる。
初期運用では経過措置により、登録・システム・管理態勢の整備猶予が付される公算が大きい。一方、IEOは株式CF類似の投資上限制御を導入しつつ、二次市場での上限超回避にどう向き合うかが論点だ。
背景
海外レンディングの連鎖破綻が生じたため、国内でも借入形式の抜け穴と相まって利用者保護強化が急務となった。
2025-01時点で国内口座数は1,214万超に達し規模が拡大する一方、国内では「事業者がユーザーから借りる」形式により交換業の分別管理義務が及ばない欠陥が指摘されてきた。実際に国内大手の一部サービスは「交換業ではないため分別管理対象外」「期間中は返還不可」等を明記しており、事業者倒産時の返還不能リスクが顕在化していた。海外では2022年にCelsiusやVoyager、Vauldが破綻し、顧客資産に甚大な損害を与えたことも判断材料となった。
市場への影響
短期は利回り縮小やコスト増で資金循環が鈍る一方、長期は透明性と信頼が向上し参入の広がりが期待される。
国内交換業者は金商法対応の登録と内部管理強化でコスト負担が増すため、採算の厳しい中小は縮小や再編の可能性がある。他方、明確な枠組みは銀行・証券グループの参入や機関投資家対応を後押しし、国内のプロダクト供給能力を底上げする。海外無登録業者の締め出しで個人の高リスク商品への流入は抑制される一方、利回り低下で一部はDeFiなどオンチェーンへ回避する動きも想定される。
論点とリスク
規制は国内オフチェーン中心のためDEX等オンチェーン統制には限界があり、過度な規制は海外流出を招く一方で、緩すぎれば保護が弱まる。
有識者からは、制度導入直後は「運用の柔軟性」を確保すべきとの意見や、オンチェーン規制の限界を報告書に明記すべきとの指摘があった。業界側も信頼確保には賛同しつつ、過重な事務負担と費用対効果の乖離を警戒しており、実効性とコストの均衡が問われる。
今後の注目点
報告書の文言確定と条文化の精度が最終的な負担水準を決めるため、IEO上限の実効性やDEX UIの本人確認義務の設計が焦点となる。
2025年末の最終報告→2026年前半の法案提出→可決後の省令・ガイドライン策定で、分別管理や信託保全、広告規制の細目が固まる。施行後は自主規制機関の審査やモニタリング強化が併走し、事業者の態勢整備の成否がユーザー資産の安全度を左右する。
▽ FAQ
Q. レンディング規制で何が変わる?
A. 金融庁案(2025-11-07)で金商法監督へ移行し、分別管理や再貸付・ステーキングのリスク説明を義務化する方向です。
Q. IEOの投資上限は?
A. 年50万円超は年収または純資産の5%まで、上限200万円を想定する案で、株式型CFの仕組みを参照しています。
Q. 施行スケジュールは?
A. 2025年末に最終報告→2026年前半に法案提出→2026〜2027年にかけ順次施行の見込みです。
Q. 規制対象の線引きは?
A. 不特定多数の公衆を相手にする貸付が対象で、対公衆性のない機関投資家間の相対貸借は除外案です。
Q. 背景の破綻事例は?
A. 2022年にCelsius、Voyager、Vauldが相次ぎ破綻し、顧客に大きな損害が生じたことが契機の一つです。
■ ニュース解説
金商法での監督化はプロダクトの「金融商品化」を進めるので、開示・広告・市場監視と保管管理を一体で強化できる。
投資家の視点:利回りだけでなくカストディと説明体制を重視し、IEOは上限・流動性・二次市場の価格乖離を前提に参加可否を吟味したい。
※本稿は一般的な情報提供を目的としており、投資助言ではありません。
(参考:金融庁)