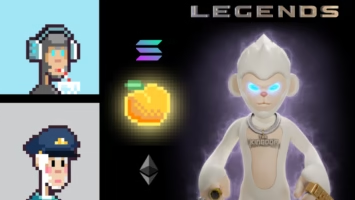▽ 要約
国内初の円連動ステーブルコインJPYCが10/27発行開始
JPYC EXで発行・償還、13:00開始・KYCはJPKI
手数料は発行・償還・送金無料(ガス代除く)
Ethereum/Avalanche/Polygon対応、1日100万円上限
JPYCが2025-10-27に正式発行、公式プラットフォームJPYC EXで円↔JPYC交換が始まり、手数料無料とマルチチェーン対応で実需拡大が期待される。
日本円に1:1で連動するJPYCが2025-10-27に正式発行され、公式プラットフォーム「JPYC EX」も同時公開される。発行・償還・送金は当面無料で、Ethereum等に対応し、法人決済や国際送金の即時性・コスト改善が見込まれる。8月の資金移動業登録を経て制度対応が整ったことで、円建てステーブルコインの実用段階が日本で初めて立ち上がる。
JPYCの正式発行とJPYC EXの公開(2025-10-27)
8月の登録取得を受け2025-10-27 13:00に発行とEXを開始するため、円↔JPYCのオン/オフランプが国内で初めて常時稼働する。
発表は2025-10-24、発行開始は2025-10-27で、ユーザーはJPYC EXで発行予約→銀行振込→登録ウォレットに発行、逆に償還予約→指定アドレスへ送付→登録口座に払い戻しとなる。発行・償還・送金の手数料は当面無料(ガス代除く)で、裏付けは預貯金と日本国債が発行残高の100%以上を保全する設計だ。KYCはマイナンバーJPKIで非対面完結。
要点(時系列)
2025-08-18に資金移動業登録、2025-10-24に正式リリース発表、2025-10-27に発行開始とEX公開が続き、初期は機関投資家需要を想定する。
当初の運用では発行・償還は1回3,000円以上、1日100万円までに制限される一方、ユーザー間送金・保有に上限はなく、P2Pや法人決済での高額利用にも道が開かれる。
背景(制度・産業・技術)
改正資金決済法でステーブルコインが「電子決済手段」に区分されたため、資金移動業者等が円換価性と準備資産の保全を条件に発行できる体制が整った。
JPYCはこの新制度に基づく国内初の円建てステーブルコインで、発行体は利息収入(預貯金・国債)を主収益源に手数料無料モデルを掲げる。対応チェーンはEthereum/Avalanche/Polygon(順次拡大予定)で、開発者向けに無償のJPYC SDKも提供され、発行・償還APIや残高取得などが容易に実装可能だ。
市場への影響(価格・流動性・フロー)
ドル建てが約99%を占める市場に円建ての選択肢が加わるため、クロスボーダー決済やキャリートレードで円需要の新たな受け皿となる。
国債と預貯金で裏付ける運用は、残高拡大に応じてJGB需要を創出しうる一方、発行・償還のフローが国内の円流動性に与える影響も注視すべきだ。即時・低コスト送金は企業間精算や為替ヘッジの実務を効率化し、アジアのライトレール(準速決済)としての役割拡大が見込まれる。
論点とリスク(賛否の整理)
当面の発行・償還は1日100万円上限のため流通立上げは漸進的となる一方で、準備資産運用・チェーン選定・規制変更が主要リスクとなる。
スマートコントラクトやブリッジ等の技術リスク、償還資金の流動性管理、オンチェーン分析とAMLの高度化、会計・税務の整合、USドル建市場との相互運用性などが論点だ。透明性の高い開示と監査、準備資産の安全・流動性確保、障害時の償還優先手順の明確化が信認の鍵となる。
今後の注目点(時系列)
EX稼働後の発行残高の伸びと対応チェーン拡充、銀行・大企業の受入れ、3年で10兆円目標の進捗と開示頻度が注目点となる。
近時は国内メガバンクの安定通貨構想も報じられており、相互運用標準と決済接続の整備次第でユースケースが拡大する。海外では米国の連邦ルールや香港の発行ライセンス制度が進むため、クロスボーダー対応と規制適合のスピードが競争力に直結する。
関連:JPYC手数料ゼロの真相:円建てステーブルコインの収益設
▽ FAQ
Q. JPYCの発行開始はいつ?
A. 2025-10-27 13:00(JST)にJPYC EXが公開され、円↔JPYCの発行・償還が開始される(初日は混雑想定)。
Q. 手数料は?
A. 発行・償還・送金は当面無料で、発行体は国債等の利息で運営。ネットワークのガス代は別途必要。
Q. 上限や本人確認は?
A. 発行・償還は1回3,000円以上・1日100万円まで、ユーザー間送金は上限なし。KYCはマイナンバーJPKI。
Q. 対応チェーンは?
A. 初期はEthereum・Avalanche・Polygonに対応し、企業接続やSDK連携で順次拡大予定。
Q. 発行規模の目標は?
A. 公式には3年で10兆円規模の発行残高を目指す。機関投資家・法人決済の需要取り込みが鍵。
■ ニュース解説
制度整備を背景に民間発の円建ステーブルコインが実装段階に入ったため、円のデジタル化が国際送金・法人決済の即時性とコストに実務的な改善をもたらす一方で、残高拡大に伴うJGB需要や償還時の流動性管理が新たな観察点となる。
投資家の視点:公式EXでの償還性・開示の継続性、準備資産の安全性、チェーン別の運用コスト、海外制度との相互運用、発行上限の段階的緩和や第1種取得動向をチェック。
※本稿は一般的な情報提供を目的としており、投資助言ではありません。
(参考:JPYC株式会社)