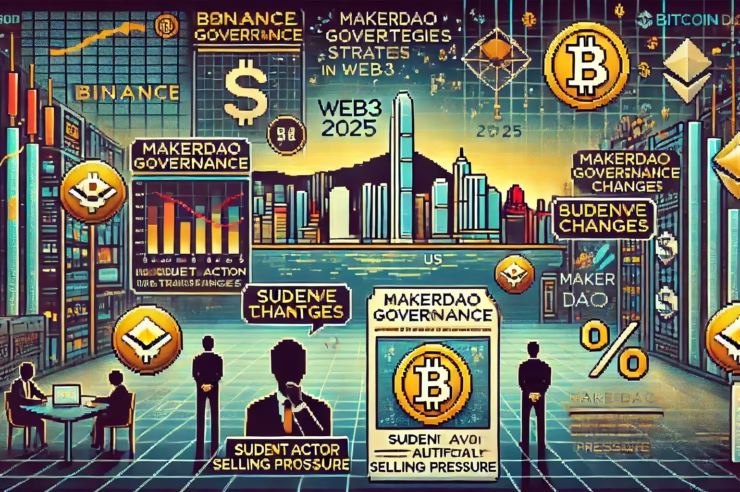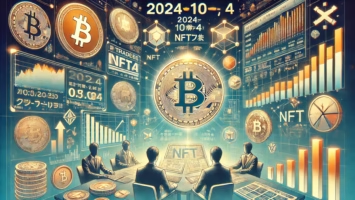【要約】
・イーロン・マスク氏がトランプ前大統領と「DOGE分配」構想を協議か
・Binance.USはドル建て取引や入出金を再開し、今後段階的にユーザーへの提供を拡大
・ニュースによれば、ナイジェリア政府がBinanceを相手取り、経済損失815億ドルおよび脱税を理由に訴訟
・MakerDAOで突如としてガバナンス提案が可決され、MKR担保の借入限度額や清算比率などが大幅に変更
・「Web3で成功するには“発言するより沈黙が重要”」とする視点が浮上
・ビットコイン価格は「人為的な売り圧力」で抑えられている可能性が指摘
・香港で開催された「Consensus 2025」では、Web3規制と実需をめぐる最新動向が注目の的に
Binanceをめぐる新たな展開:米国とナイジェリアの動き
暗号資産(仮想通貨)市場において最大手とされるBinanceは、規制当局の厳格化により国・地域ごとに対応を迫られてきました。Binance.USは、2025年2月19日付で一時停止していたドル(USD)の入出金および取引サービスを再開し、今後数日間でより多くのユーザーに解放すると発表しています。具体的には、銀行口座からのACH(自動振替)による手数料無料の入金、ドルと暗号資産の相互交換、さらには定期的な自動購入機能も復活する見込みです。
一方、ナイジェリアの訴訟は、同国での暗号資産取引がナイラ下落を加速させたとして、815億ドルもの賠償金と20億ドルの納税をBinanceに求める大規模な内容と報じられました。ナイジェリア政府はすでにBinanceの責任者2名を拘束した経緯があり、国際的な暗号資産企業に対する圧力としては非常に注目度が高い事例です。
こうした動きは、暗号資産が依然として既存の法定通貨や金融システムに与える影響が無視できない規模にあることを示唆しています。そのため、Binanceを含む大手プラットフォームが規制当局とどう折り合いをつけるかが、今後の暗号資産市場の方向性を決定づけるカギとなるでしょう。
マスク氏とトランプ氏の「DOGE構想」は実現するのか
イーロン・マスク氏はSNS上で、トランプ前大統領とともに「DOGE分配」について検討する意向を示唆しました。投資会社AzoriaのCEOによる提案で、連邦政府の「DOGE(Department of Government Efficiency)」が節約した財源の一部を、アメリカ納税世帯に5,000ドルずつ還元するという構想です。
この「DOGE」という名称は暗号資産のDogecoinを連想させるものですが、実際には政府支出の削減から生まれた余剰資金を還元する案という点が特徴的です。マスク氏は当初「最終決定は大統領次第」と述べましたが、そもそも現政権はトランプ氏ではありません。実現の可否は不透明ながらも、マスク氏の一挙手一投足が市場に与える影響力は依然大きく、今後の進展によってはDogecoin価格などにも波及効果を与える可能性があります。
MakerDAO:突発ガバナンス提案で浮上する中央集権化リスク
DeFi(分散型金融)の代表格であるMakerDAOでは、MKRトークンを担保にUSDSを借りられる仕組みのうち、借入限度額の引き上げや清算比率の大幅な引き下げなどが、緊急提案としていきなり可決されました。具体的には、MKRの清算比率が200%から125%へと大きく変更され、さらにMKR預け入れ時のデット上限(借入限度額)も2,000万USDSから4,500万USDSへ拡大。一方で、安定手数料は12%から20%に上げられています。
提案のきっかけは「ガバナンス攻撃の防止」とされましたが、コミュニティメンバーからは具体的根拠が乏しいとの批判が集中。反対意見を唱えたユーザーや団体がフォーラムやDiscordで発言を制限される事態も生じたと報告されています。DeFiは本来、分散的かつ透明な意思決定を目指すはずですが、今回のMakerDAOの動きは一部の大口保有者が権力を握っているのではないかという懸念を強めています。
「Web3では沈黙が重要」:発言リスクと情報戦略
「Web3沈黙法則――人は言葉を覚えるのに2年、沈黙を学ぶのに一生」という一節が話題を呼んでいます。暗号資産やWeb3の世界では、注目を浴びることが資金調達やトークン価格に直結しやすいため、SNSを通じて積極的に発信するプロジェクトや個人が多いのが現状です。しかし、その反動として誇大広告や根拠の乏しい発言が批判や規制のターゲットとなるケースも増えました。
記事によれば、特に大手の取引所や著名プロジェクトほど、一度の失言や炎上が全体の信頼喪失につながりやすいという指摘があります。さらに、競合他社や金融当局の監視が強まる中、情報管理や広報戦略はこれまで以上に「言わない勇気」を求められるようになっているのです。Web3が今後さらに大衆化するにあたり、プロジェクトの評価は熱狂だけではなく、プロフェッショナルな「沈黙」のバランスも問われるでしょう。
ビットコイン価格の「人為的な抑制」説
あるアナリストは、ビットコインの買い圧が高まっているにもかかわらず価格が上昇しにくいのは、FTXなど破綻した企業の資産整理や、破産管財人による売却が続いているためだと指摘しました。特にFTXはおよそ2万ドル付近でのビットコイン売却を原資とした債権者への補償を進めているとされ、これが中古のビットコインに一定の売り圧力を作り出しているといいます。
また市場全体で見ると、マイニング関連の資金繰り、破産企業の救済や負債返済などが相次ぎ、投機的な上昇を相殺する要因が多いのが現実です。短期的には、この“人為的な売り”が継続することにより、ビットコイン価格が伸び悩む可能性がある一方、長期的にみれば健全な需給バランスが形成され、あるタイミングで大きく価格が動くシナリオも考えられます。
香港での「Consensus 2025」:RWAと規制の最前線
香港で開催された大規模カンファレンス「Consensus 2025」は、世界中のWeb3関係者が一堂に会する注目のイベントとなりました。特に、香港政府は独自の規制フレームワークを次々と打ち出しており、Web3分野の新興企業や伝統金融機関との協業が活発化しています。以下のポイントが大きく議論されました。
- 法定通貨を裏付けとするステーブルコイン
渣打香港やCircleが港元ステーブルコインを構想していると報じられるなど、ドル以外のステーブルコイン開発が進みつつあります。香港金融管理局(HKMA)も、こうした取り組みを「規制サンドボックス」的に支援し、新たな決済・送金手段としての実用化を検討中です。 - RWA(Real World Assets)のトークン化
不動産、国債、貴金属などの実世界資産をブロックチェーン上でトークン化し、効率的な流動性や透明性を確保しようという動きです。香港ではすでにグリーン債券や貿易金融に適用するトライアルも進行しています。これにより、伝統金融とDeFiが実質的に融合し、より多くの投資家層が参入しやすくなることが期待されています。 - 持続的な規制進化
香港は仮想資産交換所(VATP)のライセンス制度を2024年以降に本格施行しており、ETFやOTC市場についても相次いで整備が進んでいます。米国がトランプ政権下で対暗号資産規制姿勢を若干緩める方針を示唆しているなか、香港は国際金融センターとしての優位性を保ちつつ、安全性とイノベーションを両立させる模索を加速させているのです。