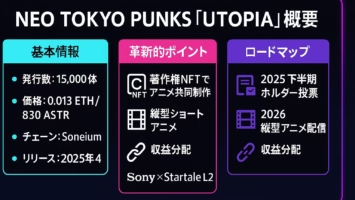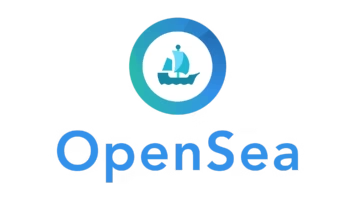【要約】
・OpenSeaが7年にわたる浮き沈みの末、ついに独自トークン「SEA」を発行へ
・一時はNFT取引所のトップだったOpenSeaだが、Blurなど新興勢力の猛追でシェアを大きく落とす
・過去の成功要因、そして転落の背景を探りながら、今回の「SEAトークン」がNFT市場全体に与える影響を考察
・「OS2」ベータ版のリリースや多チェーン対応など、再浮上に向けた戦略を多角的に分析
・OpenSeaの動きがNFT市場の再起動や競争激化を促すかに注目が集まる
新たな潮流を予感させるOpenSeaの発コイン
かつて「NFT取引所の王者」と称されたOpenSeaが、このたび独自のプラットフォームトークン「SEA」を発行すると発表しました。2月13日深夜、OpenSea公式アカウントがSNS(X)上で新バージョン「OS2」のパブリックテスト開始とともにSEAトークンのリリースを示唆し、「空投(エアドロップ)が行われる可能性がある」と言及したことで、瞬く間にコミュニティの注目を集めました。まだ発行スケジュールや詳細は明かされていないものの、発表直後からユーザーの期待値は高く、コメント欄やリツイート数はあっという間に四桁に到達しました。
長らく「ユーザーへのトークン還元」を行わず、IPO(新規株式公開)の噂さえ取り沙汰されていたOpenSeaが、ここにきてなぜ「SEAトークン」を選んだのか。NFT業界全体が低迷する今、OpenSeaの狙いはどこにあるのでしょうか。本記事では、OpenSeaの7年にわたる興亡史を振り返りつつ、今回の発コイン計画がNFT市場全体にどのようなインパクトをもたらすかを深掘りしていきます。
NFT取引所のトップに上り詰めたOpenSeaの栄光と没落
1-1.2017年:CryptoKittiesに見るNFT勃興のきっかけ
OpenSeaの物語は、CryptoKittiesに端を発するNFTブームと不可分です。2017年末、イーサリアム上で登場した猫のコレクションゲーム「CryptoKitties」が思わぬ熱狂を生んだことで、NFT(Non-Fungible Token)という概念が世界的に認知され始めました。Devin Finzer氏とAlex Atallah氏はこのタイミングを捉え、2018年2月にNFTに特化したマーケットプレイス「OpenSea」を設立。ブロックチェーンや暗号資産の熱狂期であった一方、NFT自体はまだ黎明期であり、顧客をつかむのは容易ではありませんでした。
1-2.初期競合:Rare Bitsとの対比
設立当初からOpenSeaは同業のRare Bitsとしのぎを削っていました。Rare Bitsはゼロ手数料や取引時のガス代補填など、ユーザーにとって一見魅力的な施策を打ち出しましたが、結果として運営コストがかさみ、2018年から2019年にかけての暗号資産市場低迷期を乗り越えられませんでした。一方OpenSeaは、当初1%(後に2.5%)と一定の手数料を設けて堅実な収益モデルを確立。「時間はかかってもNFTに特化した取引所を続ける」という方針に徹し、少人数でコツコツと開発・運営を行ったのです。
1-3.2020年:再起の兆し
2020年になると、加密通貨(暗号資産)全体が徐々に回復基調に入りました。OpenSeaも懸命のテコ入れを続け、「懶惰(らんだ)ミンティング(Lazy Minting)」の導入によりクリエイターが手数料を最小限に抑えてNFTを発行できる環境を整備。さらにアート、音楽、域名など多種多様なNFTを網羅し、クリエイターもユーザーも参入しやすい「オープン」なマーケットプレイスを志向しました。これらの地道な施策が功を奏し、徐々に取引量が増加。Rare Bitsなど競合が相次いで撤退していく中、OpenSeaは生き残りを果たしたのです。
一大ブーム到来:月間取引量数十億ドルの頂点へ
2-1.2021年:DeFi熱からNFT熱へ
2021年前半はDeFi(分散型金融)の勢いが強く、NFTはまだニッチな存在にとどまっていました。ところが年央以降、BAYC(Bored Ape Yacht Club)などのPFP(プロフィール画像)系NFTが記録的な価格上昇を見せはじめ、市場は一気にNFTモードにシフト。OpenSeaは流動性と品揃えの豊富さからユーザーを抱え込み、月間取引量はあっという間に数十億ドル規模にまで拡大しました。2022年1月には取引量が50億ドルを突破し、名実ともに「NFT取引所のトップランナー」となったのです。
2-2.驚異の収益とチーム拡大
当時は手数料2.5%というビジネスモデルが大当たりし、チームはわずか数十名ながら月単位で数千万ドルの収益をあげていました。投資家もこぞってOpenSeaに注目し、2021年から2022年初頭にかけて巨額の資金調達を達成。評価額は133億ドル(日本円で1.7兆円以上)にまで膨れ上がり、まさに時代の寵児といえる存在でした。
転機:IPO報道とユーザーの不満
3-1.Web3理念との乖離
そんなOpenSeaが転落へ向かう分岐点の一つが「IPO計画」の噂でした。2021年12月に米配車大手Lyftの元CFOがOpenSeaに参画し、「IPOを検討している」旨を示唆したことでコミュニティは一気にヒートアップ。多くのWeb3支持者は、トークンを発行しコミュニティに還元することが筋だと考えており、「IPOはWeb3の理想に反する」という批判の声が高まりました。OpenSeaも正式発表こそ避けたものの、「IPOの可能性は排除しない」という曖昧な立場を取り続けたのです。
3-2.吸血鬼攻撃:LooksRareなどの台頭
OpenSeaが依然としてトークンを出さない態度を示した結果、多くのプロジェクトが「発コイン」を武器に市場シェア獲得に動きました。2022年初頭に登場したLooksRareは、OpenSeaユーザー向けに空投を実施し、さらに取引手数料を独自トークン「LOOKS」で還元するという大胆策を打ち出します。これがいわゆる「吸血鬼攻撃(Vampire Attack)」と呼ばれる手法です。一時はLooksRareの取引量がOpenSeaを上回る事態となり、OpenSeaの「絶対王政」は揺らぎ始めました。
Blurの登場と「NFT市場の新王」誕生
4-1.革新的UIと空投策
最終的にOpenSeaの牙城を大きく崩したのが、「Blur」の台頭でした。2022年10月に正式ローンチされたBlurは、トレーダー向けに最適化されたUIや、積極的な空投(Airdrop)を武器に急速にユーザーを獲得。OpenSeaのような「マーケットプレイス」的な設計ではなく、NFTを株や暗号資産のように素早く売買できる「トレーディングプラットフォーム」に近い操作性を提供し、プロトレーダー層を取り込みました。
4-2.NFT市場の崩壊とShift
Blurが登場した頃には、暗号資産全体が「冬の時代」に突入し始めており、NFT市況もすでにピークを過ぎていました。そんな中でBlurは空投をテコに劇的な取引量増加を達成しますが、大口投資家による大量売買が目立ち、一般ユーザーの多くは相次いでNFT投資から撤退。「ガチホ(長期保有)」文化が希薄になったことで市場はさらに冷え込みました。その結果、Blurが取引量で市場1位となり、OpenSeaは勢いを失っていったのです。
起死回生を狙うOpenSea:SEAトークンの真意
5-1.巻き返しの方策
業績悪化とともにOpenSeaは、買収話が持ち上がるほど苦境に立たされていました。しかしここにきてOpenSeaがリリースした「SEAトークン」の発行は、自社のブランド力を再浮上させる切り札となる可能性があります。具体的には、Blurなどが得意としてきた「空投活用型のコミュニティ醸成」を取り入れることで失地回復を図るとみられます。既にテスト版として発表された「OS2」では手数料を0.5%に引き下げ、Blurのゼロ手数料戦略に対抗する意志を鮮明にしているのです。
5-2.市場が期待する「再点火」のシナリオ
OpenSeaがかつての栄光を取り戻すには、単に「トークンを配る」だけでは不十分です。Blurの強みは、高速な取引性とUIのわかりやすさにあるため、OpenSeaもそこを改良しなければユーザーは戻ってきません。その一方で、OpenSeaの知名度や多チェーン対応への積極姿勢は依然として圧倒的なアドバンテージです。OS2はFlow、ApeChainなど複数のブロックチェーンを横断するNFT取引を目指しており、SEAトークンがマルチチェーンで利用できる「共通通貨」の役割を果たす可能性も期待されています。
NFT市場へのインパクト:再活性化となるか
OpenSeaが発行する「SEAトークン」は、自社の起死回生策であると同時に、市場全体を再活性化するカギとなるかもしれません。実際、今回の発表後、OpenSeaの1日あたりの取引量は一時70%超のシェアを記録し、NFTコミュニティ全体の注目が再び集まっています。Blurも今後新たなキャンペーンやトークン施策を打ち出す可能性が高く、相互の競争がさらに激化すれば、停滞気味のNFT市場がもう一度活況を取り戻すシナリオもあり得るでしょう。
ただし、LooksRareやX2Y2など、過去にトークン配布で注目を集めたプラットフォームも、その後失速した事例は少なくありません。結局、ユーザーが求めるのは「利益と流動性」であり、それを提供できるプラットフォームだけが生き残るという厳しい現実があるのです。
OpenSeaとBlurの「二強対決」が当面のNFT市場を牽引していくのか、あるいはMagic Edenのように独自チェーンで強みを持つプラットフォームがさらなる躍進を遂げるのか。いずれにしても、OpenSeaが満を持して投入するSEAトークンが、新たな火種となるのは間違いありません。NFT市場の次のステージを占う上でも、大いに注目しておく価値があるでしょう。