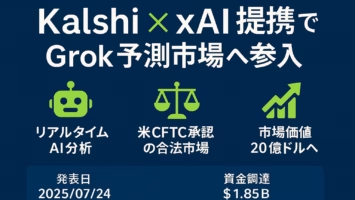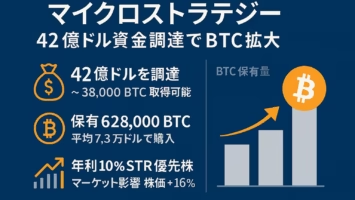▽ 要約
市況 ETF流出−$566.4M、BTC一時$100k割れ
政策 中国が対米24%関税を1年停止、英は規制案
企業 Rippleが$500M調達・評価額$40B、鯨のETH買い
イベント Balancer余波でxUSD乖離、BEX資金$12.8M回収
ビットコインETF流出が続いたため、11月6日の市場は$100k攻防とマクロ・規制の織り込みが焦点となった。
市況総括
ETF流出が続いたため、2025-11-05にBTCは一時10万ドルを割り込み、200日線(約$109.8k)も下回る場面があった。
米現物BTC ETFは11/4のネットフローが−$566.40M(FBTC −$356.58M、ARKB −$128.07M、BITB −$7.10M、EZBC −$8.72M、IBITは±$0)と報告され、需給は短期的に逆風となった。さらに過去30日でLTHが約327,000 BTCを放出したとの分析や、平均生産コストが約$114,000に上昇している点も下押し材料である。
レンジ・需給の見方
テクニカルでは101,000ドル維持が強気構造の目安と指摘され、下値は$104,000の再テスト観測もある一方、ETFフロー反転が鍵となる。
CryptoQuantは「日足で$101k維持が買い場示唆、割れは構造毀損の恐れ」と整理し、10/末〜11/初のETF資金反転(10月前半+、月末−)が投資家センチメントの温度計になっている。
規制・政策アップデート
米中関税の緊張が緩和したため、株式・暗号資産のリスクセンチメントは改善しつつも、制裁やルール整備は継続している。
中国は対米24%追加関税の1年停止を発表、米株は「関税は合法」との最高裁判断観測後退で上昇した。加えて、米OFACは北朝鮮関連54アドレスを新規制裁。英国はステーブルコイン規制で個人£20,000/法人£10,000,000の一時保有上限を想定し、米国と歩調を合わせると伝えられた。
企業・資金調達・プロジェクト動向
資金調達とトークン施策が続いたため、個別ニュースは強弱まちまちだが資金循環の芽は残る。
Rippleは$500Mを$40B評価で調達との速報。Jupiter DAOは1.3億JUPのバーン可決、Berachain BEXは$12.8Mの資金回収を報告。SuiLendはStream Finance問題でdeUSD貸出$68Mへの対応を公表し、「7 Siblings」は過去2日で37,971 ETHを調達した。
BSCの脆弱性とGIGGLEの急騰急落
注意喚起が不足したため、インフルエンサー発言を契機に価格が短時間で乱高下し、BSC全体の脆弱性が露呈した。
CZの発言を受けたGIGGLEの急騰急落は、注意と流動性に過度依存する市場構造の歪みを示した。短命化するテーマ循環の中で、情報の真偽とリスク許容度の見極めが一層重要となる。
イベント
DeFiの連鎖反応が広がったため、xUSDの乖離や貸付市場の金利急騰リスクが顕在化した。
Balancer V2脆弱性を起点に、Stream FinanceのxUSDが目標価格から乖離。SuiLendはElixirに返済要請、BEXは機能制限を継続しつつ資金回収を進める。マクロではADP(ミニ雇用統計)が米政府閉鎖下の「数少ない指標」として注目される。
▽ FAQ
Q. BTCはいつ10万ドルを一時的に割れた?
A. 2025-11-05未明(JST)に下抜け、同日内に回復。短期支持は$101,000、200日線は約$109,800。
Q. 11/4の米現物BTC ETFのネットフローは?
A. 合計−$566.40M(FBTC −$356.58M、ARKB −$128.07M、BITB −$7.10M、EZBC −$8.72M、IBIT ±$0)。
Q. 英国のステーブル規制の方向性は?
A. 米国と同歩調、個人£20,000・法人£10,000,000の上限を想定し来年以降に本格施行へ。
Q. Rippleの資金調達は?
A. $500Mを$40B評価で実施との速報。流動性環境の再評価につながる可能性。
Q. DeFiで気を付けるべき点は?
A. オラクル設計と償還可能性、PoR開示、連鎖清算の経路。xUSD乖離と連鎖の教訓。
■ ニュース解説
ETFからの資金流出が続いたため、短期需給は悪化した一方で関税緩和や規制の見通しが改善し、政策要因はリスクオンに傾きやすい地合いとなった。Arthur Hayesの「ステルスQE」観測もドル流動性の再拡張を示唆するが、DeFiの連鎖リスクは残存する。
投資家の視点:フロー(ETF・鯨・先物OI)と政策日程(関税・規制・雇用統計)をモニターし、$101k/$104kの価格節目、レンディング担保のオラクル仕様、PoRの有無を逐次点検する非裁量ルールを整備したい。
※本稿は一般的な情報提供を目的としており、投資助言ではありません。
(参考:PANews)