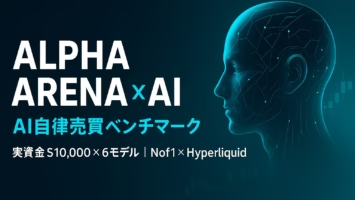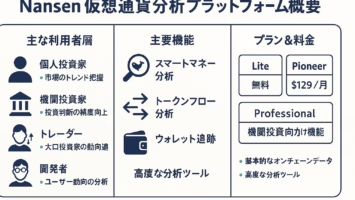【要約】
・AI Agentの分野が再び活発化し、MCP、A2A、UnifAIといったプロトコルが登場
・DeFiなどでの実装例が拡大し、複数のAgentが連携する新たなエコシステム形成へ
・最新の資金調達ニュースや技術アップデートを確認し、今後の進展を見極めることが重要
近年、AI技術の進化は目覚ましく、ブロックチェーン上で展開されるAI Agent(エージェント)も大きな注目を集めています。特に2025年に入り、MCP(Model Context Protocol)やA2A(Agent-to-Agent Protocol)、UnifAIなどのプロトコル標準が相互補完的に結びつき、**「Multi-AI Agent」**という次世代の相互通信インフラが形成されつつあることが話題です。本記事では、AI Agentがどのように“第二の春”を迎えつつあるのか、そして最新のニュースを踏まえて何が起こっているのかを詳説いたします。
MCP(Model Context Protocol)の役割と課題
MCPとは?
MCPはAnthropicが中心となって開発・提唱しているオープン標準プロトコルで、AIモデルと外部ツールをつなぐための共通「神経系統」のような役割を担っています。ここで注目すべきは、異なるLLM(大規模言語モデル)でも共通の関数呼び出し形式を用いて外部サービスへアクセスできる点です。まるでWebの世界で「HTTPプロトコル」が担ってきた標準的通信のように、Web3 AI領域の通信の統一化を狙うものといえます。
技術的意義と残る課題
MCPは大きな可能性を秘める一方、遠隔地との安全な通信や認証、特に資産が絡むデータのやり取りなど、セキュリティ面の課題も依然として指摘されています。
たとえば、TEE(Trusted Execution Environment)を活用したセキュアな実行環境をどのようにMCPに組み込むか、@SlowMist_Teamや**@evilcos**といったセキュリティ専門家もレポートで詳細な分析を公開しており、今後の改善が期待されるポイントとなっています。
A2A(Agent-to-Agent Protocol)の可能性
エージェント間の「社交」プロトコル
Googleが主導するA2Aは、AI Agent同士を効率よく連携させるための通信プロトコルです。いわば**「Agent間の社交ネットワーク」を築くことを目的としており、AtlassianやSalesforceを含む50社以上の企業が賛同を表明しています。
MCPが「AIモデルと外部ツール」間の連携に注力する一方、A2AはAgent同士の協調や能力発見**を重視しています。具体的には「Agent Card」という仕組みにより、各AI Agentの保有する機能や知識を相互に共有しやすくなる設計です。
Googleが握る主導権
A2Aの技術的価値もさることながら、Googleがこのプロトコルを後押ししている事実が大きな注目を集めています。標準化の恩恵に加え、大手テック企業のバックアップは、市場浸透を後押しする大きな要因となるでしょう。
UnifAI:MCPとA2Aを融合する「中間層」
統合型エージェント協作ネットワーク
UnifAIは、MCPとA2Aの長所を組み合わせ、複数のAgentを横断的に利用できるプラットフォーム構築を目指すプロジェクトです。特に中小企業向けのソリューションとして打ち出されており、クロスプラットフォームでのAgent協業を円滑に進めるためのサービス発見機能が注目を集めています。
ただし市場認知やエコシステム拡大の面では、まだ他のプロトコルに比べて課題が残り、今後特定の分野にフォーカスして深掘りしていく可能性も指摘されています。
「Dark」とDeFi:MCPを活用した新たな実装
Solana×MCP×TEEの融合
興味深い事例として挙げられるのが、@darkresearchaiが開発するDarkというMCPサーバー実装です。これはTEEを活用してセキュアな実行環境を実現し、AI AgentがSolanaブロックチェーン上で安全にアカウント残高の照会やトークンの発行といった操作を行えるようにする試みです。
この仕組みにより、AI AgentがDeFi取引や流動性提供(LP管理)を自動的に実行する未来が見えてきました。Darkのネイティブトークン$DARKの価格は一時期上昇傾向を見せていますが、投資判断は慎重であるべきでしょう。とはいえ、**「実際に使える」**Agentエコシステムの一例として、大きな注目を集めています。
多エージェント協同とブロックチェーンの親和性
単独エージェントから複数協力の時代へ
A2AやUnifAIは、複数のAI Agentが協力して作業を遂行する新たな枠組みを提示しています。ブロックチェーンならではの分散構造と合わせることで、**「個々の専門性を持つ小型AI Agentが連携し、より大きなタスクをこなす」**というビジョンが現実に近づいているのです。
DeFiに限らず、ゲーム領域(GameFAI)やクリエイティブ分野など、多様なセクターで活用される可能性があります。
安全性と協作効率が鍵
多エージェントがブロックチェーン上で連携するためには、MCPやA2Aのようなプロトコルによる標準化と、TEE等による安全な実行環境の整備が不可欠です。これらが整えば、AI Agentは情報を解析するだけでなく実行力を伴った存在へと進化し、真の意味での自律分散型AIエコシステムが形成されることでしょう。
関連ニュースと市場動向
(1)ORO AIの600万ドル種子ラウンド
DeFi特化型のAIプラットフォームを掲げるORO AIが、a16z Crypto Startup Accelerator(CSX)とDelphi Venturesから主導された資金調達で、600万ドルを獲得しました。ブロックチェーン技術を活用しつつ、プライバシーを守りながら高品質なデータをAIモデルに提供する仕組みは、今後さらなるDeFi連携を後押しすると見られています。
(2)Wayfinder登録アカウント数が100万突破
AI関連プロジェクトであるWayfinder基金会が、ユーザー登録数100万を突破したと発表しました。利用者増加は、市場の興味がAI Agent分野へ再び集まっている証左といえそうです。
(3)xAIのGrok Studioリリース
xAIが、AIを用いたコード生成やGoogle Drive統合による文書編集を共同で行えるGrok Studioを発表しました。AI Agentによる協作機能がより身近になり、オフィスワークや開発現場での利便性が大幅に高まる可能性があります。
(4)ChatGPTの画像生成ライブラリ実装
OpenAIはChatGPTに専用の画像ギャラリー機能「Library」を追加し、これまで生成した画像を一括管理できるようにしました。AI Agentの機能拡張が継続的に行われていることがわかり、ユーザーの表現力と生産性がさらに高まることが期待されます。
(5)Gliderがa16zなどから400万ドル調達
AIとDeFiを組み合わせ、ユーザーに自動化された資産運用プランを提供するGliderが、a16zやCoinbase Venturesなどから400万ドルの調達に成功しました。今後a16zの暗号資産関連アクセラレータプログラムへ参加する予定で、非カストディ型のポートフォリオ管理分野の拡大が見込まれます。
ニュースの解説
ここ数年で急速に盛り上がったAI Agent分野は、一度過剰な「MEME化」によるバブル感が生じましたが、現在はより実用的な側面へとシフトし始めています。MCPやA2Aなどのプロトコル標準化が進むにつれ、ブロックチェーンとの連携による**「安全性」と「協作効率」の高い実装が増える兆しが見えてきました。
また、DarkをはじめとしたTEE活用型のプロジェクトや、ORO AI・GliderのようにDeFi連携を具体化する例が登場したことで、単なる情報解析にとどまらない、実行力あるAI Agentの時代が近づいています。
とはいえ、いまだにスタートアップの段階にあるプロトコルやソリューションも多く、過度な投機にはリスクが伴います。大手企業の支援を受けるA2Aや、資金調達で注目度を高めるORO AI**・Gliderのような動きに注視するとともに、本質的に**「Web3とAIの融合」**を実現できるかどうかを見極めることが肝要です。
今後も、技術標準の成熟度合いと大手企業・VCの動向を見ながら、**「真に使えるAI Agent」**がどこまで進化できるのかを注視していきたいところです。文字通り“第二の春”が訪れるか否かは、これらの動きがどれだけ現実的なソリューションとして根付くかにかかっているといえるでしょう。