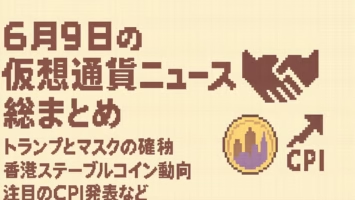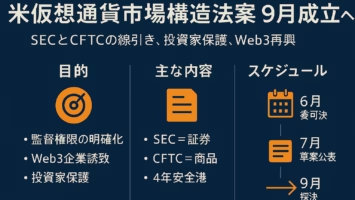▽ 要約
法制:2023年施行で発行・取扱の枠組み確立
主要:JPYC・MUFG・SMBC・GMO・SBIが台頭
戦略:マネックスが円建て発行検討と欧州買収を示唆
外国:USDC解禁で実用段階が加速
日本のデジタル決済は、円建てステーブルコインの制度化を経て2025年に実装段階へ入り、マネックスは発行検討とM&Aで主導権確保を狙う。制度・主要プレイヤー・マネックス戦略を一体で整理し、円建てステーブルコインがもたらす実務インパクトを明らかにする。
日本のステーブルコイン規制の現在地
明確化した改正資金決済法が電子決済手段としての位置づけと取扱業者制度を整備したため、国内で安全性とイノベーションの両立が進んだ。
日本では2023年6月に改正資金決済法が施行され、法定通貨と1:1償還の「デジタルマネー型」ステーブルコインを電子決済手段と定義し、その他は暗号資産等として整理された。発行主体は銀行・資金移動業者・信託会社に限定され、類型ごとに資産保全・償還義務・監督が異なる。取扱業者は登録制で、AML/KYC、トラベルルール、顧客資産の分別管理等が義務化された。
改正資金決済法の要点
銀行は預金として発行でき預金保険の保護対象となる一方、資金移動業者は保証金預託や信託保全で裏付資産の安全性を確保する仕組みが敷かれた。
取扱業者登録とトラベルルール
交換・媒介・管理を行う取扱業者には登録が必要で、送金時の情報付与(トラベルルール)や記録・監視といった金融犯罪対策が明文化された。
外貨建ての受入れ(USDCなど)
2025年3月、SBI VCトレードが取扱業者第1号登録となりUSDCの国内流通・交換を開始したため、外貨建ての実需利用も本格化した。
円建てステーブルコインの主な参入企業
銀行・IT・フィンテックが同時多発的に参入し、ユースケースと規模に応じた棲み分けと相互運用の設計が進む。
JPYC(資金移動業者)
2025年8月に資金移動業者の認可を取得し、年内に「JPYC」を発行予定で、国内預金と日本国債で100%裏付け、手数料無料・利息収入モデルでの展開を掲げる。
メガバンク(MUFG・SMBC)
MUFGは「Progmat Coin」で信託型・預金型の発行基盤を整備し、DatachainやSoramitsuとともにチェーン間相互運用の実証を進める。一方SMBCはAva Labs・Fireblocks・TISと商用化の共同検討を開始した。
IT・フィンテック(GMO・SBI・Soramitsu)
GMOはNYDFS認可の円建てGYENを海外で運用し、国内展開のSaaS化も視野に入れる。SBIはCircleと連携してUSDCの国内普及を推進し、RippleとはRLUSDの日本展開で合意。SoramitsuはBakongを軸にアジア横断の決済ネットワーク構想を主導する。
マネックスグループの円建て発行計画と戦略
先行プレイヤー台頭の中、取引・証券の顧客基盤と国債裏付けをてこに、送金・法人決済から普及を図る狙いだ。
計画の概要(発行目的・用途)
松本大会長は円建て発行の検討を認め、日本国債等で裏付ける1:1償還型を想定する。用途は国際送金や法人決済を軸に、グループ内(コインチェック・マネックス証券)での交換・決済導線を整備して流動性を確保する。
発行体制・技術選択肢
発行主体は資金移動業者型の取得、または信託会社との連携が現実的で、チェーンはEthereum等のパブリック採用が見込まれる。裏付け資産は主にJGBとし、発行量に比例する利息収入で低コスト運用が可能になる。
シナジーと普及戦略
コインチェックは2024年12月にNASDAQ上場(CNCK)を果たし、本人確認済み口座220万の顧客基盤を持つため、上場・交換・決済の一体運用で初期流動性を確保しやすい。B2B決済と越境送金の実需を先に取り、後段でWeb3やNFT決済に広げる構想が現実味を帯びる。
欧州企業の買収計画
欧州のブロックチェーン企業買収の最終調整を示唆しており、技術・人材・ライセンスの取り込みでグローバル展開と国内実装の両輪を強化する狙いだ。
市場展望—競争・規制・ユーザーへの影響
取扱いと相互運用の標準化が進むため、用途別に複数の円建てが併存しつつ、利便性と信用力でデファクトが形成される。
競争の行方
メガバンクは企業・機関決済、フィンテックは小口決済・送金に強みが想定される一方、相互運用(銀行預金トークンや他チェーン)を担保するネットワーク設計が勝敗の鍵となる。
規制・国際動向
国内は利用者保護とイノベーション促進の両立を継続し、2025年の米国GENIUS法成立で国際的な制度協調も現実味が増す。CBDCとの共存射程でガイドライン微修正が続くだろう。
ユーザーへの影響
24/7即時送金・低コスト・スマートコントラクトの自動決済で、個人・企業のキャッシュマネジメントが刷新される。選択肢増加に伴い、発行体の信用と準備資産の透明性が選定基準となる。
▽ FAQ
Q. 日本の円建てステーブルコインは誰が発行できますか?
A. 銀行・資金移動業者・信託会社の3類型で、1:1償還と資産保全・AML/KYCが必須(金融庁・2023年6月施行)。
Q. JPYCはいつ発行され、裏付け資産は?
A. 2025年秋に「JPYC」を予定、銀行預金と日本国債100%裏付けで円と1:1交換、当初は機関需要を想定。
Q. USDCは日本で使えますか?
A. 2025年3月にSBI VCトレードが第1号登録を取得し、USDCの交換・送金サービスを開始済みです。
Q. マネックスのステーブルコイン構想の狙いは?
A. 国債裏付けの円1:1通貨で国際送金・法人決済を効率化し、コインチェック等の顧客基盤で普及を狙います。
■ ニュース解説
2023年施行の制度整備で国内発行・取扱の道筋が明確になったため、2025年はJPYC認可やUSDC解禁で実装が加速する一方で、相互運用と標準化が次の論点となる。
投資家の視点: 決済・送金・トークナイズド資産の基盤銘柄として、発行体の信用・準備資産・償還条件・連携エコシステム(取引所・決済事業者)を定量比較するのが実務的です。米GENIUS法や国内ガイドライン更新など規制の進展は需給面に影響するため、政策・ライセンスのニュースフローをモニターしましょう。
※本稿は投資助言ではありません。
(参考:金融庁,Financial Services Agency(英),SBI VCトレード)