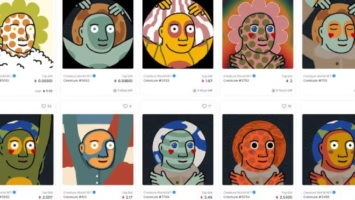▽ 要約
新会社:SBIとStartaleが株式トークン化の新会社。
時期:2026年後半〜2027年に投入予定。
強み:顧客五千万件とODX/STARTを活用。
国際:欧州のRobinhoodとKrakenが解禁。
株式の決済・名義書換・コーポレートアクションをオンチェーン化できれば、手数料とタイムラグは大幅に縮む。SBIはStartaleと組み、SBI 株式トークン化 新会社で既存の証券・清算レイヤーを再設計し、2026〜27年の実装を視野に次世代基盤を狙う。本稿では、目的・スキーム・制度論点・海外比較・KPIまで一次情報で整理し、国内事例(ODX「START」)やSBIの顧客基盤を踏まえ、実装現実性とリスク低減策を立体的に解説する。
新会社の目的とスキーム
株式の権利表示と移転をブロックチェーンで一貫管理し仲介を圧縮するため、SBIとStartaleは低コスト・即時性の市場基盤を共同開発する。
新会社の狙いは、発行・保管・移転・配当等の証券ライフサイクルをスマートコントラクトで統合し、T+数日→秒〜分の権利確定を標準化することだ。StartaleはAstarで培ったL1/L2設計やStartale Cloudのオーケストレーション、SonyとのSoneium開発で得た運用知見を提供し、SBIは証券・銀行・暗号資産・信託のライセンス群と顧客動員で実装を加速する。
予定タイムラインと到達目標
制度・システム・運用の審査を順に通すため、限定銘柄と適格投資家での実証から始め26年後半〜27年の段階提供を狙う。
初期は非上場または限定流通銘柄から着手し、配当・議決権・名簿管理の自動化を優先、二次流通はパブリック/許可型のハイブリッドで試行する。実需の鍵はフェイルセーフな権利保全と相互運用性であり、監視・セーフモード・停止条件と再開手順を予め設計する。
既存アセットの動員(ODX/START・顧客基盤)
STARTの二次市場実績とSBIの五千万件超の顧客を動員できるため、オンボーディングと実務接続で先行優位を得やすい。
2023年12月25日開設のSTARTは日本初のST二次市場として実績を積み、商品多様化が進む。SBIは証券・銀行・信託・暗号資産交換業の接続性を活かし、KYC・適合性・税制・配当実務をワンストップに寄せやすい。
技術・運用アーキテクチャの要点
許可型原簿と公開型/L2の接続で厳密な権利記録と相互運用を両立するため、二層構成と鍵管理の抽象化を中核に据える。
カストディはアカウントアブストラクションでUXを改善し、多署名/ハードウェア混在で冗長性を確保。データはイベントログ→原簿同期の不可逆パイプで記録し、緊急停止・ロールバック・ガバナンス投票の運用フローを事前定義する。
ガバナンスとカストディ
鍵紛失や誤送信などの救済と監査証跡を制度化するため、KYCホワイトリストと多署名・保険・バックアップ原簿を併用する。
さらにSLA/監査を明確化し、障害時のコーポレートアクション代替実施と最終権利の整合を担保する。
規制と制度の論点(日本)
FIEAや会社法等と改正資金決済法を整合しDVPを実装するため、発行者責任と名簿・保管・救済の分担を明確化する。
株式トークン化では、発行者・名簿管理人・保管/移転責任の明確化、誤配布・ハッキング救済の制度設計、相場操縦/インサイダーへの統合対応が求められる。2023年6月1日施行の改正資金決済法は電子決済手段(ステーブルコイン)の枠組みを整備し、オンチェーンDVPの実装に資する。
海外動向と比較
ブローカーは欧州RobinhoodとKrakenが株式トークン取引を解禁し、運用会社はBlackRockとFranklinがトークン化ファンドを拡大した。
市場は「株・ETFそのもののトークン化」と「ファンド持分のトークン化」の二流で拡大し、24/7移転・オンチェーン配当/利息・相互運用が差別化要素となる。
取引所・ブローカーの動向
EUや非米圏を起点に提供を拡大したため、即時決済と低手数料が訴求点となり個人投資家の参入障壁が下がった。
米国内規制の制約を回避しつつ、KYC済み域内に限定して提供する方式が主流だ。
トークン化ファンドの進展
BUIDLは24年3月開始後にAUM10億ドル超へ、BENJIはP2P転送を拡張したため、オンチェーン利息と企業財務利用の実需が強まった。
オンチェーン配当/日次利息や複数チェーン展開は、トークン化資産のユーティリティを実証し、担保・流動性管理への応用を広げている。
リスクと対処
法規・保護・技術・受容性の四層に分けて対処するため、契約・運用・UIと教育を重ね救済と可観測性を制度化する。
- 法規:発行体・原簿管理人・市場運営者の責任分界、開示/インサイダーの整合。
- 保護:誤送信救済、バグ時のロールバック、保険/補償基金の設計。
- 技術:監視/監査ログ、冗長化、チェーン停止時の代替決済。
- 受容性:ウォレットUXの非カストディ/カストディ両対応、鍵管理の抽象化と教育で心理ハードルを下げる。
ロードマップとKPI
PoC→限定公開→拡大の三段でKPIを開示し信頼を積むため、可用性・清算失敗率・自動化率・オンボーディング数を年次管理する。
- 年0〜1:限定銘柄、名簿/配当/議決の自動化率≥90%、清算失敗率≤10⁻⁴。
- 年1〜2:二次流通拡大、DVP完全自動化、月次SLA 99.95%。
- 年2〜3:海外投資家参入の拡大、相互運用API一般提供、監査報告を年2回化。
▽ FAQ
Q. 新会社の狙いは?
A. SBIとStartaleが株式をトークン化し、手数料低減と即時決済を実現する次世代市場を構築すること(26〜27年投入)。
Q. どの基盤を活用?
A. StartaleのStartale CloudやSoneiumの知見と、SBIの**ODX「START」**や信託・証券の実装力を組み合わせる。
Q. 具体的効果は?
A. T+数日→秒〜分の権利確定、24/7移転、海外投資家の参入容易化、配当/権利処理の自動化が期待される。
Q. 顧客基盤は?
A. 2024年3月末5,000万件超(SBIグループ)。ODXや信託機能と合わせ、大規模オンボーディングが可能。
Q. 海外の先行は?
A. Robinhood(EU, 2025/7)とKraken(非米国, 2025/7)が株式トークン取引、BUIDL/BENJIがファンド持分のトークン化を牽引。
■ ニュース解説
TV東京報道でSBIとStartaleの株式トークン化新会社計画が示されたため、ODX/STARTと改正資金決済法を土台に国内実装が進み、一方で欧州の事例との接続が制度・技術の焦点となる。
投資家の視点:仕様・制度が確定するまでは実需KPI(出来高、清算失敗率、配当自動化率)とSLA/監査の開示に注目し、クロスボーダー提供時はKYC/税務と流動性分断のリスクを点検したい。
※本稿は投資助言ではありません。
(参考:TV東京Biz,大阪デジタルエクスチェンジ,SBI Integrated Report 2024(英))