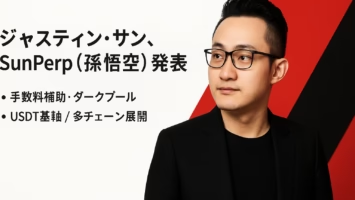▽ 要約
スーパーアプリ|2027年度公開を目標に、決済・運用を一体化
レンディング利回り|BTC/ETH8%、USDT等10%を想定
規制・ガバナンス|セルフカストディ+登録業者連携で適法化
トレジャリー|2025年10月に10.666BTC取得、年内大幅拡大へ
暗号資産を「保有・運用・決済」まで一気通貫で使いたい――Neo Crypto Bankは、その需要に対しセルフカストディ基盤と提携群で応える構想である。2027年度の公開を掲げ、SlashやJ‑CAMと連携し、レンディング利回りを支払い体験にまで接続するのが特徴だ。Neo Crypto Bankの意義と実現性、利回りの現実性と規制面の要点を、一次情報に基づき解説する。
スーパーアプリ「Neo Crypto Bank」の全体像
セルフカストディを軸に資産保管・決済・送金・運用を統合するため、ウォレットとレンディング、カード、オン/オフランプが段階的に接続される。
ウォレットはユーザー自身が秘密鍵を管理する非託児設計を前提とし、クレジットカードはSlash Cardを取り込む想定だ。これによりUSDCやJPYC等のステーブルコインを担保・残高として日常決済へ回し、運用中の資産も決済に即時連動させる設計を示す。公開時期は2027年度が目標で、決済市場シェア1%(年間約4億回、1.2兆円規模)を掲げる。
組み込み機能と対応銘柄
J‑CAM/BitLendingとつなぐため主要暗号資産とステーブルコインが中心となる見込みで、BTC・ETH・XRP・SOL・USDT・USDC・DAI等が候補となる。
実装は段階的で、オンランプ(円→ステーブル)とオフランプ(ステーブル→円)の仲介、チャット・配車・ホテル等外部サービス連携を広げ、将来的にはDeFiや証券投資アクセスまでを視野に入れる。
預けるだけで増える仕組み(利回りの源泉)
ユーザー資産をレンディング運用に回し、その収益の一部を貸借料としてユーザーに配分するため、高い利回りが提示できる。
Neo Crypto BankはJ‑CAMのBitLendingと戦略連携し、アプリ預入→運用→利息配分の導線を担保する。2025年10月時点の貸借料率はBTC/ETH年8%、XRP年7%、USDT/USDC/DAI年10%で、返還手数料は年4回まで無料などの条件が明示されている。
運用の想定手法とセキュリティ
複数の機関・取引先と分散した運用でポートフォリオ最適化を図るため、相対的に高い料率が確保される。
セキュリティはFireblocksのMPCやOff‑Exchange/コラテラル運用を活用し、取引所破綻・ハッキング時の資産隔離と運用効率の両立を狙う。一方で中身の詳細は非公開領域も多く、開示レベルと透明性の継続が重要となる。
利回りの現実性と比較・安全性
国内取引所の貸出年率は概ね0.1~5%であり、7~10%は国内最高水準であるため、収益源は市場運用に依存しリスクも相応に大きい。
DeFiレンディングの実勢はステーブルコインで4~6%前後、BTC系は1%未満が一般的で、高料率はインセンティブ次第で変動する。過去の海外CeFi破綻例(CelsiusやBlockFi)は、高利と不適切なリスク管理の両立の難しさを示した。
主要リスク(価格・信用・流動性・制度)
暗号資産の価格変動で円換算元本割れが起こり得るため、利回りと相殺で損益が振れる。
貸出先の信用・連鎖破綻、引出制限や返還手数料、スマートコントラクトやカストディ障害等の技術・運用リスク、そして制度変更・当局方針の影響も受ける。ユーザーは「利息ではなく貸借料」である点と非保証を理解し、分散と上限設定を徹底したい。
イオレの最新動向と実行計画
Slash Visionと資本業務提携し、Slash Cardの国内法準拠・セルフカストディ型カードを取り込むため、決済と運用の接続が加速した。
2025年10月1日には国内レンディング最大級BitLending運営のJ‑CAMと戦略提携、10月7日には199,999,542円で10.666BTCを初回取得し、年内120~160億円規模の取得とレンディング投入を明言。10月14日には暗号資産金融事業の戦略発表会を開き、Neo Crypto Bankの詳細ビジョンと関係各社との協業方針を公表した。
関連:イオレ×Slash Vision資本業務提携、協業開始
財務・資金調達とBTCトレジャリー
2025年はPIPESで最大約4.2億円を調達し新規事業へ配分、9月には新株予約権スキームを通じた大規模調達枠を設定した。
BTCトレジャリーの拡大と運用益、カード・決済手数料、レンディング収益のシェア等、複合収益モデルを積み上げる方針で、最終的に1兆円規模のバックアセット構築を目標とする野心的な青写真を示す。
規制・許認可とプロダクト設計
交換業は登録事業者との連携で実装し、ウォレットはセルフカストディで提供するため、顧客資産の直接預託を回避して適法性を担保する。
FINX JCrypto(関東財務局長第00012号)との協業検討で交換業ノウハウを取り込み、ステーブルコインのオン/オフランプは電子決済手段等取引業の枠組みも意識し、設計上の準拠性を高める。最終的には当局との調整・登録取得の進捗が実装速度を左右する。
本格ローンチまでの論点
カード発行(BINスポンサー・割販法対応)、オン/オフランプ(資金決済法対応)、レンディング(開示とガバナンス)、海外DeFi接続(適格性とジオフェンス)の4点を同期的にクリアする必要がある。
事業の成功には、料率・流動性・UXの最適点を市場環境に合わせて動的に作り直せる運用設計と、継続的な可視化(運用レポート、四半期開示)が欠かせない。
▽ FAQ
Q. Neo Crypto Bankはいつ公開予定?
A. 2027年度の公開を目標に、2025年10月14日にビジョンを示した。
Q. 提示利回りの根拠は?
A. BitLendingの貸借料率(BTC/ETH8%、USDT等10%)に基づく。
Q. 法規制はどうクリアする?
A. セルフカストディ設計と交換業者(FINX JCrypto)連携で対応。
Q. 初回のBTC取得は?
A. 2025年10月7日に199,999,542円で10.666BTCを取得した。
Q. 国内他社との違いは?
A. 取引所の年率0.1~5%に対し、レンディング連携で7~10%を狙う。
■ ニュース解説
構想はセルフカストディ×カード×レンディング連携で運用益を決済へ橋渡しするため、2027年度ローンチを掲げつつ2025年に資本提携とBTCトレジャリーを進めた。背景に国内規制の整備とステーブルコイン普及があり、一方で高利回りの裏側に市場運用・信用・流動性のリスクが残る。
投資家の視点:短期は資金調達とプロダクト接続の実行力、料率の持続性、開示の透明性が評価軸。ユーザーは利回りだけでなく返還条件やカウンターパーティ分散、価格変動耐性(円建て評価)を事前に確認したい。
※本稿は一般的な情報提供を目的としており、投資助言ではありません。