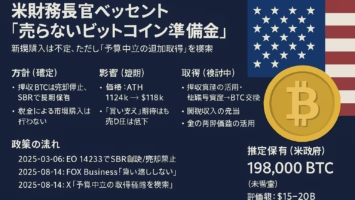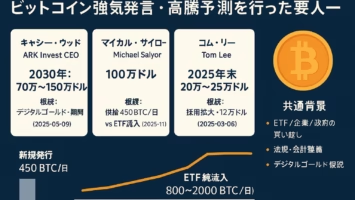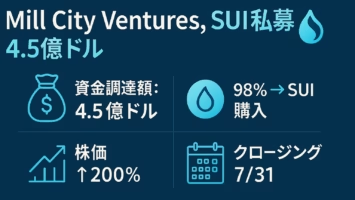▽ 要約
買得 103BTCを17.36億円で取得、平均単価は約1,686万円
保有 総保有は1万8991BTCに到達、BTC利回りは年初来479.5%
債務 第19回社債を30億円繰上償還、無利息社債で柔軟運用
論調 海外報道は概ね中立〜肯定、長期保有戦略を評価
追加取得の規模や評価は妥当か――その答えは、取得額17.36億円で103BTCを積み増し、総保有1万8991BTCへ到達した事実と、同時に無利息社債の一部30億円を繰上償還した財務運営にある。メタプラネットの「メタプラネット 103BTC 追加取得」は、攻めと守りを両立しつつBTCトレジャリー戦略の一貫性を示した。
今回の103BTC追加取得の要点
取得額は約17.36億円・平均単価は約1,686万円のため、保有総量は1万8991BTCとなった。
同社は8月25日に追加取得を公表し、1BTCあたりの平均購入価格は約113,491ドル相当、総取得額は約11.69百万ドルと整理されている。これにより通算の平均取得単価と取得総額も更新された。
取得価格・平均単価・公表日
平均単価が直近相場より上振れでも、保有の厚みが将来キャッシュフロー耐性を高めるため、追加取得は戦略範囲内といえる。
公表は日本時間8月25日。平均購入単価は円建てで約1,685万6,833円で、公式の取得履歴にも反映済みだ。累計のBTC保有・取得コストが透明に開示され、投資家の検証が可能になっている。
海外メディアの論調
取得の妥当性と株主価値の観点が強調され、全体として中立〜肯定的な受け止めが多かった。
米TipRanksやThe Block、Investing.comは取得額・平均単価・総保有を軸に「長期の株主価値寄与」に触れ、中国語圏のPANewsや鉅亨網、韓国のCoinNessも公式発表とCEOの投稿を引用し淡々と報じた。
KPI「BTC Yield」
BTC保有量/希薄化後株式数の比率の期中変化で測るBTC Yieldが年初来479.5%まで上昇した。
同社はこのKPIを定期開示し、買い増しの株主価値希釈を超える効果(アクレティブ性)を検証指標として提示している。
資金調達と繰上償還の実務
無利息・無担保の第19回普通社債を機動的に発行したため、ビットコイン購入と既存社債の整理を両立できた。
6月30日に発行した総額300億円の無利息社債は、7/7に60億円、7/15に67.5億円、8/25に30億円を繰上償還し、原資には第20回新株予約権の行使による調達金を充当している。
第19回普通社債の条件と繰上償還履歴
利率0%、償還期日2025年12月29日、EVO FUNDへの全額割当のため、金利負担を伴わずに調達・償還を反復できた。
同社は前記スケジュールで計157.5億円を繰上償還し、ビットコイン購入と第3回社債買入消却を並行して進めた。資金使途変更の適時開示により、資本市場との対話コストを低減している。
第20回新株予約権の行使状況
行使価額は連動修正条項に基づき見直されるため、市況と連動した資金流入が可能となる。
8/18〜8/22の週には4,900,000株が新規発行され、同週の行使価額は下限含みで推移した。行使資金は債務整理とBTC取得に配分され、財務柔軟性と保有拡大の両立に寄与した。
18,991BTCの意義と他社比較
世界の上場企業で上位水準のため、ビットコイン価格上昇局面では含み益が指数的に効いてくる。
ランキングでは上位常連の米マイナーや米大手に次ぐポジションで、BTCトレジャリー企業としての知名度と情報発信力が強化された。一方で価格急変動が業績・株価のボラティリティ要因となる。
市場反応と投資家センチメント
8月25日昼時点で株価は前日比+4〜5%のプラス圏で、掲示板の投票は「買い系」計約58%が優勢だった。
Yahoo!掲示板では「強く買いたい」が五割強で推移し、短期イベントドリブンの需給改善を示唆する。一方で「強く売りたい」も三〜四割台が残存し、ボラティリティを織り込む声も根強い。
▽ FAQ
Q. 103BTCはいくらで買ったのですか?
A. 約17.36億円を投じ、1BTCあたり約1,686万円で取得(2025年8月25日)。
Q. 総保有量と最新の指標は?
A. 総保有1万8991BTCで、年初来BTC Yieldは479.5%(8月25日)。
Q. 社債の繰上償還はどの程度進みましたか?
A. 第19回社債で7/7に60億円、7/15に67.5億円、8/25に30億円を実施。
Q. 長期計画の目標水準は?
A. 2026年末10万BTC、2027年末21万BTC超の段階目標を掲げています。
■ ニュース解説
103BTCの追加と同時に無利息社債の繰上償還を進めたため、保有拡大と財務健全性を両立できた。一方でBTC価格の変動が業績と株価のボラティリティ要因となる。
投資家の視点:資金調達→BTC取得→KPI(BTC Yield)での検証→債務整理という一連の回転を点検し、①希薄化速度②平均取得単価③繰上償還の進捗④外部ランキングでの相対位置を定点観測したい。ビットコイン連動の株価特性上、分散とリスク許容度の管理が重要。
※本稿は投資助言ではありません。
(参考:メタプラネット,Simon Gerovich(X))