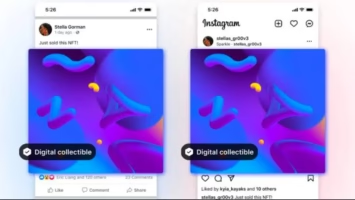▽ 要約
ゼロ手数料:利息収入により当面ゼロを維持。
技術と保全:USDC互換+国債等100%超で保全。
上限制:発行体経由は100万円、自己ウォレット送金は無制限。
規制動向:第一種・取引業の取得で大口・仲介を拡大。
発行・償還手数料ゼロは持続可能なのか——日本初の円建てステーブルコイン「JPYC」は、裏付け資産の利息収入を軸にゼロ手数料で普及を狙う。登録(2025年8月18日)と並行して技術・規制・運用の体制を整備し、当面の無料化で発行量の拡大と流通の定着を図るため、国内の決済・送金・資産運用に新たな選択肢を与える。
発行・償還手数料ゼロの背景と狙い
利息収入が発行体の主収益となるため、発行・償還手数料を当面ゼロに設定し普及速度を高める戦略となった。
JPYCは裏付け資産(円預金・日本国債)からの金利収入を主収益とし、岡部CEOは「足元の金利で1兆円発行なら年約50億円の利息収入」の試算を示す。これによりユーザー手数料を抑えて発行量拡大へ繋げる設計で、ゼロ手数料はネットワーク効果を狙った初期戦略と位置付けられる。
金利環境とブレークイーブンの直感
短期金利が正の環境下では発行残高の拡大に応じて利息が逓増するため、スケール獲得ほど収益余地が拡がる。一方で金利低下局面では無料維持の余地が狭まる。
日米の金融情勢は変動しうるが、国内では国債収益で原資を確保しつつ、決済普及を優先する戦略が採られている。
技術・運用スキーム(チェーン、発行体制、保全)
JPYCはUSDCと同規格のスマートコントラクトとSDKで実装され、Ethereum/Avalanche/Polygonに初期対応する。
JPYCは第二種資金移動業(登録番号:関東財務局長第00099号)で、電子決済手段として発行。ユーザーはマイナンバーKYC後に日本円を入金し、同額のJPYCが即時に自身の外部ウォレットへ発行される。
分別管理と100%超保全
発行総額の101%を目安に円預金・日本国債等で保全し、分別管理(信託・供託)を徹底するため、迅速償還用に一部は信託銀行の円預金として確保、残部は国債で運用する。
MUFG信託とProgmat Coinのスキームも併用しうる体制で、信託型の「JPYC(信託型)」連携が告知されている。
ノンカストディとウォレット接続
ユーザーは自己管理ウォレットでJPYCを受取り、WalletConnect対応により主要ウォレットと接続できる。一方で秘密鍵管理の自己責任と凍結・ブラックリスト等の対策設計への理解が必要だ。
上限設計——送金・償還の実務と影響
発行体が関与する為替取引には第二種の枠として「1件100万円」の上限があるため、大口の法定通貨出入りには運用上の工夫が要る。一方で自己管理ウォレット間の送金は上限対象外である。
JPYC EX経由の円⇄JPYCは1件100万円だが、セルフウォレットに移した後のオンチェーン送金は億円単位でも可能。企業決済での円転では複数日に分ける等の実務が当面必要になる。
上限撤廃へのロードマップ
第一種資金移動業の取得で1件上限を撤廃し、貿易決済・大口資産移動への適用拡大を見込む。併せて「電子決済手段等取引業」を取得し、ブローカー/プラットフォーム機能の展開も計画されている。
規制と監督——電子決済手段の位置づけ
JPYCは暗号資産ではなく改正資金決済法の「電子決済手段」に該当し、額面償還義務と安全資産100%超の分別保全が求められる。アルゴ型の発行は禁止である。
2025年8月18日に国内初の円建てステーブルコイン発行者として登録が確認され、制度下での発行・償還が可能となった。
監督当局との関係と追加ライセンス
発行体はAML/CFT・内部統制等で厳格な監督対象となる。今後、電子決済手段等取引業(現状SBI VCトレードが保有)を得れば、他社SC流通の仲介も自社で担える。
USDC・USDTとの比較(通貨建て・規模・透明性)
円建てのJPYCは国内決済・円建て送金を主眼に、USDC/USDTはグローバルUSD需要に支えられるため市場規模は大きい。2025年9月時点で安定通貨の時価総額は約3,000億ドルに接近している。
透明性では、USDCは月次の第三者保証と週次開示、USDTは近年T-Bills中心にシフトし四半期のアテステーションを公表、JPYCは法により裏付け資産の範囲と分別が厳格に定義される。
エコシステム連携と相互補完
JPYCはUSDCと同規格・SDKで互換性が高く、CircleはJPYCに出資実績がある。国内ではUSDCの取扱いが進み、円・ドルのネットワーク接続が進展している。
ユースケース展望(決済・海外送金・運用)
国内外の小売・B2B決済、仕送り等の国際送金、DeFiでの円建て流動性供給に適するが、受け手側の円転手段やUI/UXの平易化が普及の鍵となる。
銀行営業時間に依存せず即時処理でき、手数料はブロックチェーン手数料が中心。国際送金では既存ネットワーク比で大幅なコスト短縮が期待される。
市場・政策環境の外生リスク
一部法域では安定通貨の研究・推奨が抑制される動きもあり、各国規制の差異が国際展開の課題となる。また国内CBDCは未決だが実証は継続中で、民間SCとの役割分担が論点である。
▽ FAQ
Q. JPYCの発行・償還手数料は本当に無料?
A. 2025年8月18日の登録後、当面ゼロ。1兆円で年約50億円の利息収入を見込み無料維持の原資とする。
Q. 法的区分と償還ルールは?
A. 電子決済手段に該当し、1 JPYC=1円での額面償還と円預金・国債等での100%超保全・分別管理が義務付けられる。
Q. 送金上限「100万円」はどこに効く?
A. 発行体が関与する送金・償還に1件100万円上限。自己ウォレット間オンチェーン送金は対象外で上限なし。
Q. 初期対応チェーンと開発者支援は?
A. Ethereum・Avalanche・Polygonで開始予定。USDC互換のコントラクトとSDKで数行のコード実装が可能。
■ ニュース解説
2025年8月18日にJPYCが国内初の円建てステーブルコイン発行者として登録され、利息収入を梃子に当面の発行・償還手数料ゼロを掲げ普及を加速する一方で、第二種の100万円上限が出入口に残る。
投資家の視点:制度適合・分別保全・額面償還という日本型の安全枠組みはキャッシュ代替・短期運用の受け皿になりうるが、流動性・円転動線・UI/UX・クロスボーダー規制の摩擦を見極め、第一種や取引業の取得進展、主要チェーン対応、国債運用の透明性をモニターしたい。
※本稿は投資助言ではありません。