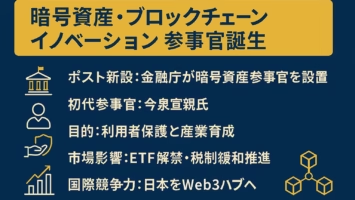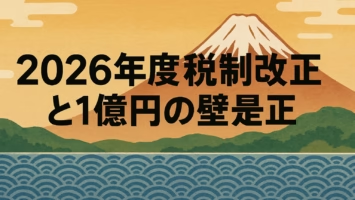▽ 要約
日本初|JPYCが2025年8月18日に資金移動業登録。
仕組み|1JPYC=1円、預貯金と国債で全額裏付け。
チェーン|Ethereum等三チェーンで今秋発行予定。
世界|USDC上場・GENIUS法成立で規制が前進。
円建ステーブルの実用段階は来るのか――結論は「来る」。日本初の法令準拠型「JPYC」が資金移動業登録(2025年8月18日)で発行可能となり、JPYC ステーブルコイン 比較の観点でも国際水準に近づいたため、制度・担保・規制の差分を押さえれば事業活用の設計が可能になる。
JPYCの制度設計と仕組み
日本の資金決済法で定義された電子決済手段に該当するため、1JPYC=1円の償還性と全額裏付けの保全が前提となった。
JPYCは資金移動業者登録(2025年8月18日)により円連動の電子決済手段を発行可能となり、裏付けは円預金と日本国債で保全され、償還は銀行振込で1:1が担保される。
発行体・保全資産・収益モデル
預貯金とJGBで発行残高相当を留保するため価格安定性が高まり、利息収入で運営する方針が採られた。
発行体はJPYC株式会社で、準備は国内銀行預金と日本国債で構成し、発行・送金手数料は徴収せず、保有JGBの利息で運営するモデルを採用する。会計上は暗号資産ではなく電子決済手段として扱われる。
対応チェーンと利用導線(JPYC EX)
複数チェーン対応のため相互運用性が高まり、本人確認と入出金導線の整備で実利用が進む。
初期はEthereum/Avalanche/Polygonでの発行を予定し、利用者はKYC後に銀行振込で受け取り、償還は1JPYC=1円での払い戻しに対応する見込みだ。
世界主要ステーブルコインの比較(制度・担保・用途)
ドル建ての法定通貨担保型が主流であるため、透明性・規制適合の差が普及に直結する。
USDT/USDC/BUSD/TUSDの多くはUSD担保の民間発行で、DAIは暗号資産超過担保、e-CNYはCBDC、EUROeはMiCA準拠のEMTと立ち位置が異なる。
主要コインの横断比較
| ステーブルコイン | 発行主体(民/公) | 担保方式 | 主な用途・普及 | 規制・方針 |
|---|---|---|---|---|
| JPYC | JPYC株式会社(民) | 円預金・日本国債100%裏付け | 国内決済・送金・Web3決済 | 資金決済法の電子決済手段、資金移動業者発行 |
| USDT | Tether Ltd(民) | 現金同等物・米短期国債中心 | 取引所・国際送金で最大規模 | 米国では連邦ライセンス外で運営、透明性は改善途上 |
| USDC | Circle(民) | 現金・米短期国債で全額準備 | 取引所・決済・法人利用が拡大 | 2025年GENIUS法の連邦枠組下、発行体はNYSE上場 |
| DAI | MakerDAO(分散型) | 暗号資産の超過担保 | DeFiで広範に利用 | 自主ガバナンス、ライセンス外のプロトコル |
| BUSD | Paxos(民) | 現金・米国債 | 取引所・DeFiで利用(縮小) | NYDFSが2023年に新規発行停止命令、償還中心 |
| TUSD | Techteryx系(民) | USD等の準備資産(実務は変遷) | 一部取引所・レンディング | 透明性・準備管理で論点、SECと2024年に和解 |
| e-CNY | 中国人民銀行(公) | 法定通貨CNY | 中国国内決済・越境実験 | CBDCとして国家主導、オフライン等を実装 |
| EUROe | Membrane Finance(民) | EUR100%準備 | 欧州決済・取引所 | EU MiCA準拠、電子マネー機関が発行 |
国際規制の最新動向(日本・EU・米・SG)
共通目的は1:1償還と準備資産の安全性確保であり、地域差は監督機関とライセンス階層に表れる。
日本は資金決済法で電子決済手段を定義し銀行・信託・資金移動業者に道を開いた。EUはMiCAでEMT/ARTを制度化し、発行主体にライセンス・準備・開示義務を課す。米国は2025年のGENIUS法で連邦ルールを整備、SGはSCS枠組で厳格要件を課す。
日本(資金決済法)
「電子決済手段」の創設で円建コインの発行主体と流通管理が明確化された。
2023年施行の改正で、銀行・信託・資金移動業者の枠組みが整い、信託型の裏付資産運用も柔軟化された。JPYCはこの枠組みを用いる先行事例になる。
EU(MiCA)
EMT/ARTの二分類により、準備・開示・償還権がEU全域で標準化された。
MiCAは2024年に主要部分が適用開始し、EUROeのように電子マネー機関が100%以上準備で発行、域内パスポーティングで普及を図る。
米国(GENIUS法)
連邦レベルのライセンスと準備・AML要件が明文化されたため、銀行・非銀行の発行体が参入しやすくなった。
GENIUS法(2025年7月成立)は、発行者のBSA遵守、1:1準備、監査・報告と償還義務を規定し、市場の標準化を加速する。USDC発行体のCircleは規制適合と市場アクセスを強化した。
シンガポール(SCS)
単一通貨ステーブルコインに限定し、準備・償還・資本要件と開示の厳格性で信頼性を担保する。
MASのSCS枠組みは、SGDおよびG10通貨ペッグを対象に、準備資産の品質・流動性と迅速償還、ホワイトペーパー開示を義務付ける。
JPYC導入がもたらす国内変化
国債需要と銀行預金の受け皿が拡張するため、決済と資本市場の橋渡し役を担う可能性がある。
JPYCを通じた円預金・JGB需要の誘発により、決済の透明性・即時性が高まり、企業・自治体のスマートコントラクト決済やWeb3公共サービスの実装が加速する一方、運用・AML/CFTの実務体制が普及速度を左右する。
▽ FAQ
Q. JPYCの償還条件と開始時期は?
A. 1JPYC=1円で銀行振込により償還可能。登録は2025年8月18日、正式発行は今秋予定。
Q. USDCの規制状況は?
A. 2025年7月GENIUS法成立で連邦枠組化。発行体CircleはNYSE「CRCL」に6月上場。
Q. BUSDの現状は?
A. NYDFSが2023年に新規発行停止命令。2025年8月も償還中心で段階的縮小。
Q. EUROeはどの枠組み?
A. フィンランドFSA監督の電子マネー機関がMiCA準拠EMTとしてEUR100%準備で発行。
■ ニュース解説
JPYCが2025年8月18日に資金移動業者登録を取得し円建ステーブルの実装が現実化したため、日本の電子決済手段制度はEUのMiCA、米国のGENIUS法と並び国際整合が進む一方で、AML/CFTや準備資産運用の実務が今後の信頼を左右する。
投資家の視点:準備資産の開示頻度・監査水準・償還SLA(営業日・カットオフ)、チェーン別ブリッジ/カストディの運用体制、対抗利用(USDC/EUROe等)との為替・手数料・決済可用性を指標化し、ユースケース別(法人口座決済/国際送金/DeFi連携)に最適化を図るのが一般的だ。
※本稿は投資助言ではありません。