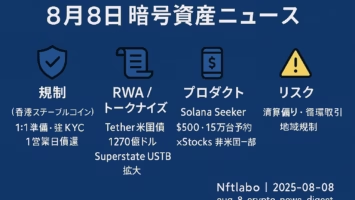▽ 要約
議連でJBAがJapan Cold Walletを提案、政府運営の一括保管案。
国内資産を集約し、海外送金・自主管理時のみチェーン送金。
現行は95%以上コールド管理、履行保証暗号資産も義務化。
賛否は二極化、単一障害点懸念と国家ブランド化の期待。
JBAが2025-11-17にJapan Cold Walletを提案し、国内資産を政府運営のコールドに集約して外部送金時のみチェーンに触れる設計でハッキング機会の最小化を狙う。
国内の暗号資産を国家管理の金庫で守れるのかという疑問に、JBAは2025-11-17、政府運営の「Japan Cold Wallet」構想を打ち出した。国内交換業者の資産を集約し、外部送金時のみチェーンに触れる設計で、ハッキング機会を最小化する狙いだ。実現すれば安全性と信頼性の一段引き上げが期待できる一方、集中管理のリスクや運用コスト、規制設計の難易度が検証課題となる。
Japan Cold Wallet構想の狙いと設計
政府主導で国内資産をコールドに集約するため、交換業者の預り資産を国家運営庫に封入し、外部移転時のみオンチェーン決済とする設計が示された。
本構想は、国内交換業者のカストディを共通インフラ化し、平常時は資産移動を抑制、ユーザーの海外送金やセルフカストディへの出金時のみチェーン送金を行う案だ。議連の場では、交換業者間の取引はネット決済(差分決済)で清算し、ブロックチェーン利用を極小化する選択肢も提示された。政府(金融庁等)が運営主体となる前提で、ライセンス設計や委託運用の枠組みが論点となる。
要点(時系列)
2025-11-17の議連でJBAが提案し、翌18日にCoinPostやCoinDesk Japanが概要を報じたため、政策議論の俎上に載った。
当日は金融庁が金商法移行の検討状況を説明し、JBAは「ネット決済」「Japan Cold Wallet」「クリプトカストディライセンス」を提示した。以後、投資家保護・市場監視と併走する形で技術・制度設計の議論が続く見込みだ。
背景
2019年以降の資金決済法改正で95%以上のコールド管理と履行保証暗号資産が義務化されたため、カストディの高度化は政策課題として一貫している。
日本では受託資産の95%以上をコールドで管理し、ホット残高と同種同量の自己資産を別途コールドに留保する規律がある。これによりFTX破綻時も日本法人の顧客資産は比較的円滑に保全・返還された。過去のMt.Gox(2014)やCoincheck NEM流出(2018)、Zaif(2018)、Bitpoint(2019)、Liquid(2021)などの被害が制度強化を後押しした経緯がある。
市場への影響
オンチェーン送金を最小化するため、国内フローはオフチェーン化が進み手数料と攻撃面が縮む一方で、出金遅延や運用コスト、ネット決済の清算設計が新たな摩擦となる。
集中管理は“平均水準の底上げ”には有効だが、出金SLAの設計、監視・アラート、異常時のハンドオーバー手順、清算金利・担保管理などのマイクロ設計がUXと流動性に直結する。さらに、各社のホット運用最適化やMPC導入といった競争的改善が標準化で鈍化する副作用もあり得る。
論点とリスク
国家が一箇所で資産を抱えるため、単一障害点・検閲・権限集中が懸念される一方で、監査の厳格化と事故時補填の可視化は信頼度を押し上げ得る。
賛成派は「投資家保護の劇的強化」「機関投資家の参入促進」「“日本は安全”という国際的ブランド形成」を評価する。他方、反対派は「非中央集権の理念に反する」「ハニーポット化」「政策・税務目的の過度な可視化」などを問題視し、セルフカストディの自由を重視する立場から懸念を表明している。
今後の注目点
金商法移行や税制改正の議論と歩調を合わせるため、2025-2026に制度要件の検討、2026-2027に実証・運用設計が現実的な道筋となる可能性がある。
短期:概念設計、責任分界、監査・ログ基盤、鍵管理(マルチシグ/MPC)指針の策定。中期:パイロット(有志数社)で入出金・清算の運用評価、SLAとBCP、障害隔離の検証。長期:メガバンク信託・DC/セキュリティベンダーとの官民連携や、保険・補償スキームの制度化。
▽ FAQ
Q. 運営主体と対象資産は?
A. 運営は日本政府(金融庁等が委託)、対象は国内交換業者の顧客資産で、原則日本居住者の保有分(2025-11-17時点想定)。
Q. 現行ルールとの違いは?
A. 現行は2019改正で95%以上を各社コールド保管、ホット分は同種同量を弁済原資として別途コールド管理する制度が日本で義務化。
Q. 利点とリスクは?
A. 国家運営でハッキング機会を極小化できる一方、単一障害点・検閲懸念や出金遅延、運用コスト増などの副作用が2025年時点で論点。
Q. いつ実現しそう?
A. 法改正と制度設計が前提で、2026年度税制議論と並走し実証→段階導入の順が現実的。早くても2026–2027年が目安と想定。
Q. ユーザーは直接使える?
A. 一般ユーザーが政府ウォレットに直接アクセスする想定はなく、接続は交換業者経由。残高証明や監査設計が2025年時点の実務課題。
■ ニュース解説
JBAが2025-11-17に政府運営のカストディ案を提示したため、金商法移行と投資家保護の文脈で「ブロックチェーンに触らない」設計が政策選択肢に浮上した。一方で集中リスクの制御と監査・退出基準が整わない限り、市場の効率性や自主管理文化と衝突しかねない。
投資家の視点:①取引所選定では鍵管理方式(マルチシグ/MPC)と監査体制を確認、②ホット残高を最小化し二段階認証・出金ホワイトリストを活用、③セルフカストディ運用手順(バックアップ/遺言/相続手当)を整備、④制度化の進捗に応じて出金SLAや手数料設計の変更リスクを織り込む。
※本稿は一般的な情報提供を目的としており、投資助言ではありません。
(参考:CoinPost,CoinDesk Japan,金融庁)