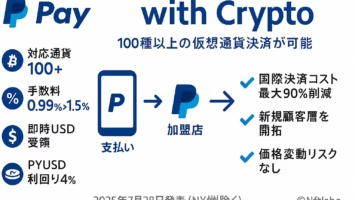▽ 要約
税制:20%分離課税と3年損失繰越の導入を要望
制度:金商法活用と投信法施行令見直しでETF解禁へ
数字:国内1,214万口座・預託5兆円で需要は顕在
時期:税は2026年、制度は2026〜2027年が軸
個人の税負担と制度不整合を正す動きが加速し、暗号資産 20%分離課税 ビットコインETFの実現性が一段と高まった。国内口座は2025年1月に1,214万を超え、預託資産は5兆円超と市場規模は明確だ。金融庁は税制要望と制度改編を同時進行で進め、早ければ2026年に分離課税、続いて制度整備により国内ETF上場が視野に入る。投資家・事業者の意思決定に直結する最新論点を解説する。
税制改正の中身と時期
税率を最大55%から一律20%へ改めるため、市場の中立性と投資機会の公平性を確保する議論が与党税調と金融庁で具体化した。
現行は「雑所得」総合課税で損失繰越不可が重いが、分離課税移行で株式等と同水準となる。要望の柱は①20%分離課税、②暗号資産損失の3年繰越控除、③交換課税見直し等で、年末の税制大綱入りなら2026年施行が射程に入る。与党・政府文書にも「資産形成に資する金融商品としての見直し」が明記された。
現行課税のボトルネック
重い累進と損失通算不可のため、短期売買に偏りや海外流出を誘発した。
総合課税は他所得と合算され最大55%に達し、ボラティリティの高い資産特性と相まって実効負担が膨らむ。分離課税化は、①税率平準化、②年度跨ぎのリスク管理(3年繰越)を可能にし、国内プレイヤーの回帰を後押しする。
スケジュール感(2025→2027)
税は2025年末大綱→法改正→2026年適用が基本線、制度は並走。
税制要望は8月末取りまとめ→年末決定→翌年度施行が通例だ。一方、制度面では市場規律(開示・不公正取引規制)との整合が鍵で、税と規制の「両輪」で環境整備が進む。
ビットコインETF承認に向けた制度・法的整備
暗号資産を投資商品として扱うため、資金決済法から金商法枠組みへの接続が俎上に載った。
金融審議会のWGが7月に始動し、情報開示、相場の公正、投資運用・助言の監督を統合的に検討。日本で「投資信託型」の暗号資産ETFを組成するには、投信法施行令で定義する「特定資産」に暗号資産を追加する政令改正が要点で、法改正を伴わず実務対応可能との専門見解が有力だ。
国内ETFの実務論点
価格発見・カストディ・AP/マーケットメーカー体制を規律で担保する。
指数連動の透明性、カバー先の価格乖離管理、受益権の設定・償還(現金/現物)方式、自己売買と利益相反の管理など、既存ETF規律の適用射程を詰める段階に入った。制度面の目処が立てば、国内証券口座からの間接投資導線が一気に整う。
タイムライン見通し
税は2026年、制度は2026年通常国会提出→段階施行が現実的だ。
WG→制度設計→政令・監督指針改訂の順で前進し、ETFは税制整備の直後に「先行解禁」のシナリオもあり得る。一方で、投資家保護と市場の公正確保が最優先となる。
国内市場への影響(投資家・企業)
税負担の平準化で投資母集団が拡大し、資金の国内回帰が進む。
20%分離課税と3年繰越はリスク管理を容易にし、長期積立・分散投資との併用余地を広げる。ETF導入でカストディ・送付先ミス等の運用ハードルが下がり、年金や公的基金など保守的資金の参入可能性が開く。国内事業者は商品開発・運用・指数・カストディのエコシステムを内製化しやすくなる。
国際比較(米国・EU・シンガポール・韓国)
米国は2024年1月に現物ETFを承認済みで、機関の保有が広がった。
EUはMiCAで包括規制を施行、スイス・独では現物連動ETP/ETNが定着。シンガポールは原則キャピタルゲイン非課税で制度を強化。韓国は2025年後半の現物ETF導入を政府が検討し、アジアでの制度競争が顕在化している。
▽ FAQ
Q. 20%分離課税はいつから始まる見込み?
A. 与党税調が2025年末に了承し法改正成立なら2026年開始が有力。3年損失繰越も並走予定。
Q. ビットコイン現物ETFは法律改正が必須?
A. 投信法施行令の「特定資産」に暗号資産を追加する政令改正で対応可能との実務見解。
Q. 国内ユーザー数と預託資産はどの規模?
A. 2025年1月時点で延べ1,214万口座、利用者預託残高は5兆円超とされる公的統計がある。
Q. 米国の現物ETFは承認済み?
A. 2024年1月にSECが承認済みで、年金基金などを含む機関の保有が1,000社超に拡大。
■ ニュース解説
税制と制度を同時に見直す方針が示され、国内市場の実勢(1,214万口座・5兆円)を踏まえ投資家保護を強化する枠組みへ移行するため、2026年の税制適用と制度段階施行が現実解となる。
投資家の視点:税率平準化と損失繰越はリスク調整後リターンの改善に寄与する一方、ETF導入後も原資産のボラティリティ・先物プレミアム・基準価額乖離など商品特性の理解が不可欠。金利・為替環境、課税区分の適用範囲、損益通算ルールの確定を注視し、分散・積立・耐久資金による段階的エクスポージャー管理を検討したい。
※本稿は投資助言ではありません。